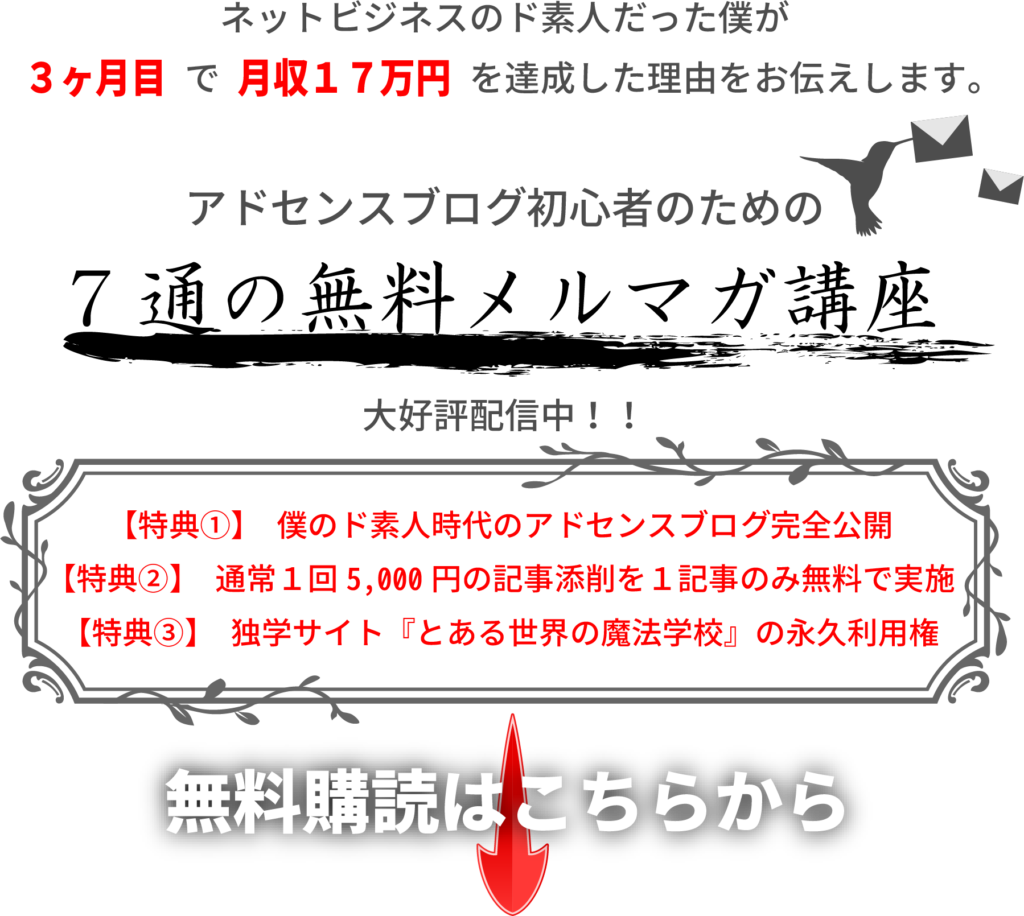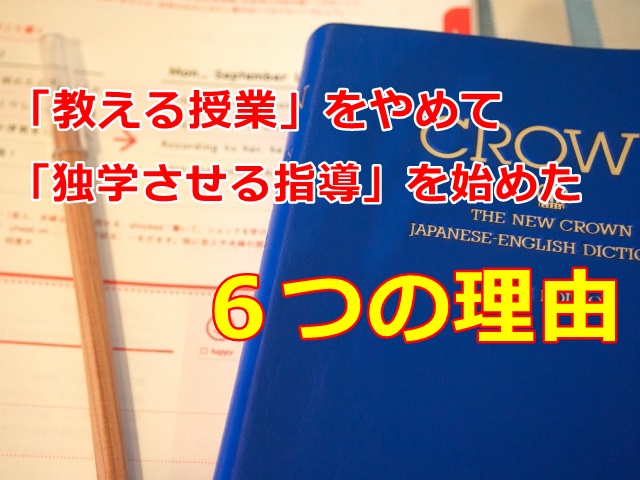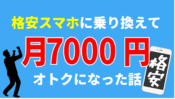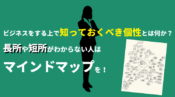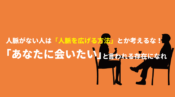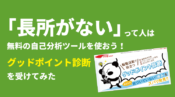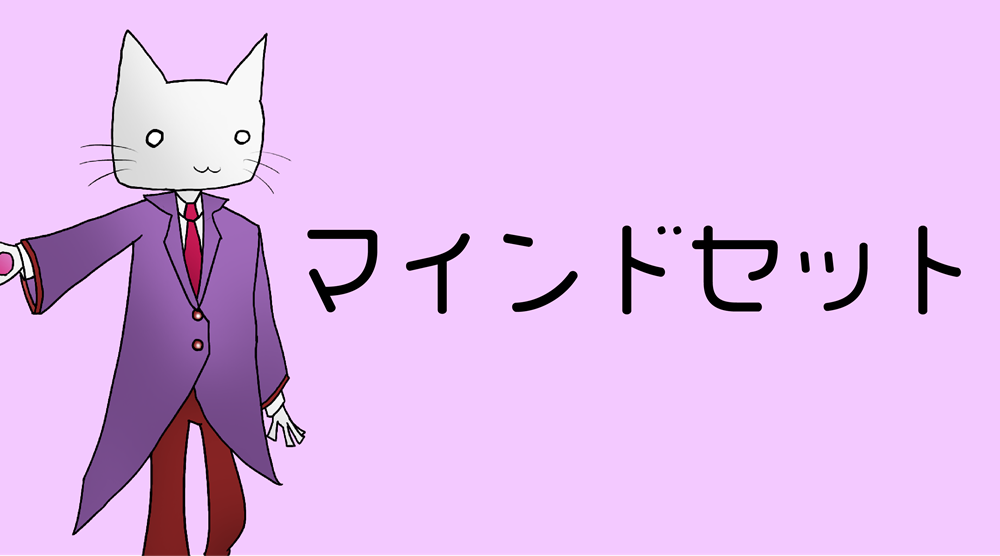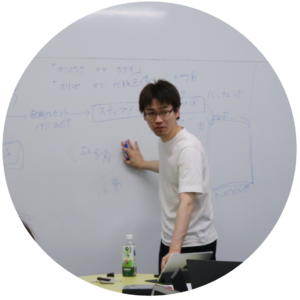センター国語の歴代問題の推移とネタ化を考察してみる
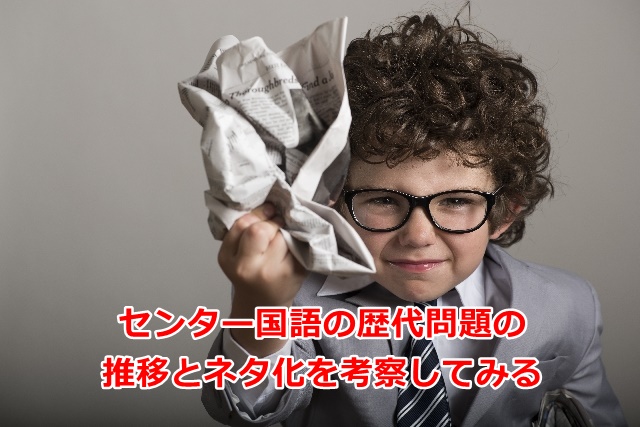
どうも、ROHIKAです。
センター国語がまた仕掛けてきたようですね。
「やおい」、「二次創作」という単語が評論に登場し、Twitterを始めとしたSNSで話題になっているようです。
数年前から、「センター国語がネタ化してきた」と言われていますが、なぜそのような現象が起こっているのでしょうか。
というわけで今回は、センター国語の歴代問題の中から注目された問題をピックアップ。
合わせて、「センター国語のネタ化」を考察してみました。
センター国語の歴代注目問題
2016年は「やおい」、「二次創作」が評論に登場し、多くの人の注目を集めました。
これに対してTwitterでは、「今年もセンター国語はやってくれた」的な投稿が殺到。
「今年も」ってことは、当然「例年」のことでもありますね。
ということで、センター国語の歴代問題を、注目株に焦点をあてて調べてみました。
センター国語の歴代問題は?
・・・と意気込んだはいいものの、文章全文を掲載するのは著作権違反です。
「歴代問題のニュアンスが伝わるものがないか」と調べたところ、次のような文章を発見。
2006年 僕っ娘百合小説
2007年 習字で告白
2008年 従姉妹を狙うイケメンに嫉妬
2009年 引越しするので家具破壊
2010年 沈黙の親子
2011年 ゴ・メ・ン・ナ・サ・イ・ネおばさん
2012年 たま虫を踏み潰すヤンデレお嬢様
2013年 スピナトップ・スピンアトップスピンスピンスピン
センター国語の要点を挙げたものとのこと。
ちなみに2014年の要点は
『おほほほほほほほほほほ あはははははははは』
2015年は
『ツイッター論』
だそうです。
どれも、これだけ見ると「なんのこっちゃ」ですね(笑)
というわけで、気になったものだけ簡単に解説していきます。
2006年 僕っ娘百合小説
登場人物は二人の女子高生。
女子高生の二人は、自分のことを「僕」と呼ぶ『僕っ娘』で、「死」に対するあこがれを抱いていました。
受験生からは「気持ちの悪い文章だった」という酷評が多かったらしく、今までに見たことのない傾向に面食らう人も続出。
最終的に一人の僕っ娘には恋人ができて、自分のことを「あたし」と呼ぶように。
文章中で、「なぜ、一人称が僕なのか」がやんわりと解説されています。
出典は、福武文庫の僕はかぐや姫。
2011年 ゴ・メ・ン・ナ・サ・イ・ネおばさん
とあるおばさんの元に市役所の人がやって来て、色んな理由から立ち退きを要求するも、聞こえないフリをした挙句に発した「ゴ・メ・ン・ナ・サ・イ・ネ」が印象的だったため、『ゴ・メ・ン・ナ・サ・イ・ネおばさん』という愛称(?)がついたそうです。
ちなみにこの「ゴ・メ・ン・ナ・サ・イ・ネ」という言葉は、真面目な文章が続く中で突然現れたため、不意打ちを食らう受験生が続出しました。
出典は、短篇集『自然連祷』より海辺暮らし。
2012年 たま虫を踏み潰すヤンデレお嬢様
主人公の男子と、仲良くなっている女子が登場。
二人がいい雰囲気になっているところ、女子が男子の胸元にたま虫が付いているのを発見するやいなや、即座にたま虫を指で弾き飛ばし、さらに即座にたま虫を踏み潰すという衝撃的なシーンがあった作品。
それまでいい雰囲気で話が進んでいた最中の出来事で、さらにこの女子が「ですわ口調」だったこともあり、「たま虫を踏み潰すヤンデレお嬢様」という愛称がつきました。
出典は、筑摩書房の井伏鱒二全集。
2013年 スピナトップ・スピンアトップスピンスピンスピン
この辺から、センター国語のネタ化が噂され始めました。
というかこれが今のところ、センター国語で一番有名なのではないでしょうか?
文章中にやたらと出てくる「カタカナ」が、何かの呪文なのではないかと思い込んでしまう受験生が続出。
「スピナトップ・スピンアトップスピンスピンスピン」の他にも、「フエーヤー」、「エンドゼエガアル」などが登場しています。
確かにこれらの言葉が急に出てきたら、一瞬思考停止してしまいますね。
呪文の正体は、英語の発音をカタカナに直したもの。
文章最後の注訳を見ておけば、何てことはないんですけどね。
それにしても強烈です。
出典は、青空文庫の地球儀。
2014年 おほほほほほほほほほほ あはははははははは
インパクトのある笑い声は本文まま。
さらにこの年のセンター国語には、「オン・ユア・マーク、ゲット・セッ」という、以前にも見たことのあるようなカタカナ英語があったり、運動用のズボンのことを「パンツ」と表記していたりと、受験生の混乱を誘うような憎い演出が多々登場しています。
出典は、青空文庫の快走。
2015年 ツイッター論
ついに現代文に、「Twitter」が登場する時代がやってきました。
これだけでもかなり衝撃的ですね。
いわゆる「クソリプ」、「パクツイ」について触れた文章となっており、案の定Twitterで大きな反響を呼ぶこととなりました。
ちなみにこの文章を書いた作者は、「クソリプ」、「パクツイ」という単語は知らず、Twitterで話題になった後から初めて聞いたそうです。
出典は、筑摩書房の未知との遭遇。
作者である佐々木敦氏は、Twitterで話題になった当時「このままだと未知との遭遇がクソリプの本てことになっちゃう泣笑」と、Twitterに投稿しています。
センター国語のネタ化を考察
一見すると世間の言うとおり、「センター国語がネタに走り出した」とも思えてしまいますが、一旦落ち着いて考えてみましょう。
「ネタのような文章が出てきた(笑)」で終わってはいけない
「センター国語がネタっぽくなってきた」、「変な文章が出題されるようになった」からといっても、センター試験自体、国単位で行っている共通試験です。
適当な意図で問題を作っているはずがありません。
たった1年くらいの「ネタ化」であれば、それはそれで「ご乱心だったのかな?」って捉えてもいいかもしれませんね。
ですがこうも連続で「ネタ化」と騒がれるような問題であれば、そこには何らかの意図が隠れているはずです。
一体どんな意図が隠されているのでしょうか。
現代化の波に乗った?
まず考えられるのが、『時代の流れに合わせて文章を意図的に変えている』ということですね。
ライトノベルや携帯小説など、文章の質が違う読み物も爆発的に増加しています。
時代の流れとともに、人々が求めている文章の質が変わりつつある。
「受験生に求める現代文力も柔軟に対応していくべきではないか」みたいな。
まあ、でも、その意図はめちゃくちゃ薄いと思います。
2013年の『地球儀』も、2014年の『快走』も、大正・昭和を中心に活躍した小説家の作品です。
(前者は牧野信一、後者は岡本かの子)
時代の流れに合わせて、ってことなら、もっと最近の小説を取りあげるべきですもんね。
受験生を混乱させる問題にしている?
もう一つ考えたのは、『受験生を混乱させる問題を選んでいる』というものです。
センター国語において、評論文は『作者の意見』、小説文は『人物の心情』を的確に読み取ることが重要になります。
文章中に「スピナトップ・スピンアトップスピンスピンスピン」などといきなり出てくると、やっぱり凄いインパクトがありますよね。
そちらの方に気が取られてしまい、本当に読み取るべきポイントが読み取れなくなる。
また、評論の方では、『いかに自分の意見を入れずに考えるか』も重要になってきます。
昨年の「ツイッター」の話、今年の「やおい」、「二次創作」の話は、多くの大学受験生にとって身近な話題です。
(後者はそこまでかもしれませんが)
自分の知っている話だからといって、「お!これは私の得意分野だ!」と自分の意見満載で解いていくと点数は取れません。
現代文では、「文章の読み取り能力」が問われますからね。
自分の考えを述べる場ではない、ということを忘れてはならないのです。
その能力を確かめるために、あえて『ネタ』とも捉えられるようなインパクトに富む文章を抜粋しているのかもしれませんね。
>>次のページは