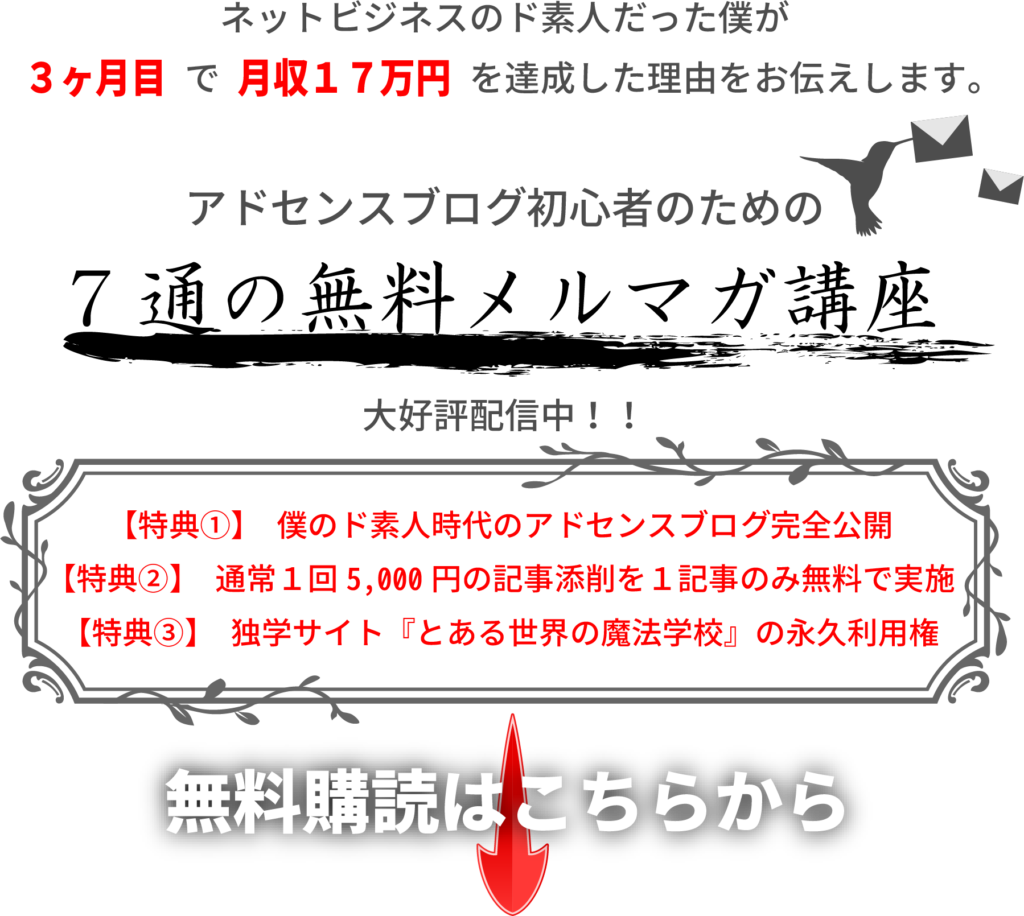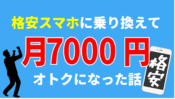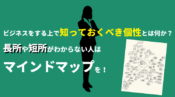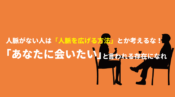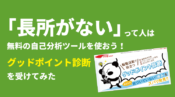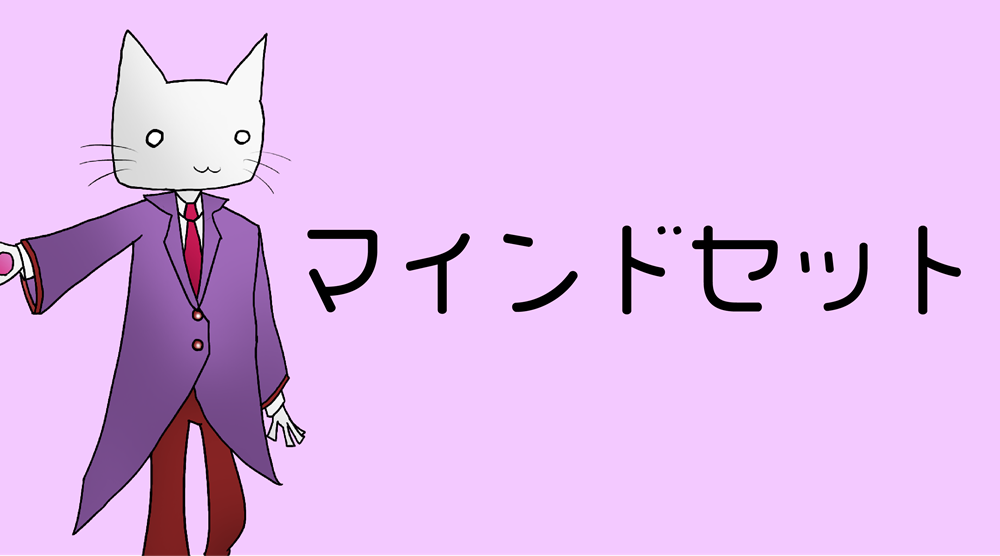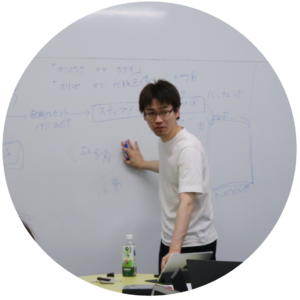もはやブログの見出しは「デザイン」だ!読者とSEOを意識した見出しのつけ方

ブログ記事において、「見出し」は「記事タイトル」の次に重要な部品です。
見出しはただの強調ではなく、記事を読み進めてもらうための「デザイン」としても機能するもの。
見出しのつけ方が最適化できれば、SEO対策にもなりますし、何よりも読者からの評価もグーンと向上します。
概要
見出しのつけ方
まずは、見出しをつけるための操作をサクッと覚えよう!

WordPressブログなら、超簡単に見出しをつけることができます。
事前に、プラグイン『TinyMCE Advanced』の設定が必要です。
設定が終わっていない場合は、以下の記事を確認しておいてください。
1.見出しにしたい文章を選択します

2.ツールバーの『段落』をクリックします

ここで『段落』が表示されていない場合は、TinyMCE Advancedの設定ができていません。
以下の記事を確認しておきましょう。
⇒TinyMCE Advancedでワードプレスの記事装飾を簡単にできるように設定しよう
3.必要な見出しを選択します

見出し自体はこれで作ることができます。
非常に簡単ですね。
ただし「効果的な見出しのつけ方」を理解するには、もう少し予備知識が必要になります。
見出しが重要な理由
ブログ記事に見出しをつけるのには、
- 読者に親切な記事をつくる
- SEO対策
という2つの理由があります。
読者に親切な記事をつくる
ブログだけじゃなくて、多くの読み物には普通「見出し」が存在します。
こんなのとかね↓

※僕の愛読書「確立思考の戦略論」の1ページです。
見出しは、「読者に対する配慮」のために設けられたものです。
どんな良書でも見出しが一切なければ、とてもじゃありませんが最後まで読み進めることはできません。
ためしに、以下の2記事を読み比べてみてください。
どちらも本文はまったく同じで、文字装飾や余白も変えていません。
違うのは見出しの有無だけです。
実際に読み比べてみれば分かりますが、見出しがないだけで非常に読みにくく感じたと思います。
読者に親切な記事を書くためにも、見出しは欠かせません。
見出しは読者にとって
- 本文の要約
- 休憩ポイント
の役割があるんです。
詳しく説明していきますね。
見出しは本文の要約
大前提として、「記事を読みたい」と思っているブログ読者はいません。
ブログ読者はみんな、「自分の疑問・悩みを最速で解決したい」という気持ちで仕方なく検索し、仕方なくあなたの記事を読んでいるに過ぎません。
できることなら記事なんて読みたくない、というのが本音です。
特に最近はスマホの読者が増えましたから、さーっとスクロールして、気になった部分だけを拾って読んでいく、という流し読みをする人がほとんど。
そのため読者に「ここが重要ですよー!」というのを、ひと目でわかりやすく伝えなければならないんです。
流し読みされることが前提なので、「流し読みでも内容が理解できる記事」をつくらなければなりません。
そのために必要なのが「本文の要約」であり、その要約こそが「見出し」になるんです。
見出しは休憩ポイント
また、それなりにじっくり記事を読んでくれる人であっても、ずっと長文を読み続けるのは疲れます。
読み疲れてしまうと、その時点で記事を閉じてしまう可能性もあります。
本であれば後から読み返すことになりますが、一度閉じられたブログ記事は二度と読み返されることはありません。
そのため必要になるのが「休憩ポイント」。
淡々と文字を書き連ねるのではなく、適所に「一呼吸おけるポイント」を設けることで、定期的に読者を休ませてあげるんです。
その休憩ポイントの代表格が「見出し」です。
見出しがあれば、「あ、ここで一段落なんだ」と読者が気づくことができます。
そこで一旦気持ちを切り替えることができるので、引き続き記事を読み進めてくれる可能性が高まります。
たとえばお経なんて読んでられないけど、途中途中に見出しがあったら多少読む気にはなるよね!多分!

SEO対策
さらに見出しにはSEO対策として、
- キーワードを伝える
- 記事構造を伝える
という役割もあります。
これも順に説明していきます。
見出しでキーワードを伝える
この記事を読んでいるということは、Google検索からの「検索流入」を狙っているはずです。
きっと、キーワード選定にも力を入れていることでしょう。
特定のキーワードを狙っているのであれば、「この記事は、○○というキーワードで検索されることを想定しています!」とGoogleのロボットに伝えなければなりません。
Googleロボットは主に、
- 記事タイトル
- 見出し(特にh2タグ)
- メタディスクリプション
から、重要なキーワードを判断しています。
絶対に押さえたいキーワードはタイトルに入れていると思います。
ですが、見出しにも自然にキーワードを加えることで、より強く「この記事は、○○というキーワードで検索されることを想定しています!」と主張することができます。
また、「タイトルには入れられなかったけど、できれば狙いたいキーワード」も見出しにいれておけば、そのキーワードで検索に引っかかりやすくなります。
見出しで記事構造を伝える
キーワードだけではなく、「この記事は、こういう流れで読者の疑問を解消していますよ!」ということも、見出しを使ってGoogleに主張することになります。
たまに『太字+蛍光ペン』など、見出し以外の文字装飾で見出しを再現する人もいますが、Googleロボットはそれを「見出し」とは判断できません。
Googleが「これは見出しだ!」と判断できるのは、コンピュータの世界の言語で「これは見出しです」と表されたものだけです。
コンピュータの世界の言語?
 ティーナ
ティーナ
と心配になるかもしれませんが、冒頭で説明した見出しのつけ方を守れば問題ありません。
専門的な言葉を使えば、「h2タグを使った文章」などと表現しますが、これも今は無理して理解しなくて構いません。
これからいろんな記事を書いていくうちに、自然と理解できるようになります。
効果的な見出しのつけ方
以上を踏まえた上で、効果的な見出しのつけ方を理解しておこう!

読者&SEOに配慮した上で、見出しをつけるときに意識すべきなのは、
- 階層を意識する
- 見出しと本文の合致
- 文章になってもOK
- 見出しで本文が推測できる
の4ポイントです。
階層を意識する
見出しには「階層」という概念が存在します。
「見出し1(h1タグ)」がもっとも大きな括りで、「見出し6(h6タグ)」が一番小さな括り。
たとえば「見出し2」は、「見出し1」の中にあるべきです。
「見出し3」は、「見出し2」の中にあるべきです。

「見出し1」の直後に、「見出し3」が登場してはいけません。
「見出し1」のあとには「見出し2」があるべきで、そのあとに「見出し3」なのです。
ですから、次のような見出しの配置はNGです。

また原則として、本文中に「見出し1」は使ってはいけません。
「見出し1」は記事タイトルのことです。
ひとつの記事内に「見出し1」が複数あると、Googleロボットが「どれが記事タイトルだ?」と混乱してしまい、正しい評価を下せなくなります。
Googleに正常な判断をしてもらうためにも、見出しの階層はしっかりと意識しておきましょう。
見出しと本文の合致
見出しは本文の要約です。
「豆乳ダイエットの方法」という見出しの中で、「豆乳ダイエットがオススメな理由」を説明してはいけません。
当たり前ですね。
だけど、この「当たり前」ができていない記事は意外と多いんです。
読者は見出しを読んだ時点で、
私は今から、○○についての情報を知ることができるんだな
 ティーナ
ティーナ
と期待して本文へと移ります。
その期待を裏切らないよう、見出しと本文内容がズレていないかは、常に確認するようにしてください。
文章になってもOK
見出しに関するノウハウ記事でよく書かれているのが、「文章はNG」というもの。
「文章はNG」という大きな理由は、「文章の見出しだと、読者はひと目で理解できないから」です。
ですが極端に長くならない限り、多少文章っぽい見出しになっても構いません。
読者がひと目で理解できない見出しであったとしても、本文を最後まで読み進めてくれれば良いんです。
僕のとある記事は、文章っぽい見出しをそこそこ使っていますが、記事の「平均滞在時間(※)」はおおよそ7分を超えています。
本文に自信があり、分かりやすい見出しであれば、多少文章っぽい見出しになっても大丈夫でしょう。
見出しで本文が推測できる
くどいようですが、「見出し=本文の要約」です。
見出しだけ読んで、本文の内容が推測できなければなりません。
少なくとも、読者が見出しを見た時点で、
私は今から、○○についての情報を知ることができるんだな
 ティーナ
ティーナ
と思ってもらえなければ、本文を読もうとは思ってくれないんです。
そもそも読者はブログ記事を流し読みするので、興味を引く見出しと出会わなければ、速攻で記事を閉じてしまいます。
見出しの前後に何が書いてあるかも、基本的に読者は気にしていません。
見出しに興味を持ってから、ようやく見出しの前後を読もうとするんです。
ですから、たとえば
「これをするには夜がベスト!」
という見出しがあったとしても、見出ししか追っていない読者は、『これ』が何を意味するのか分かっていません。
見出しだけ読んで、本文が推測できるくらいじゃないと、読者はいつまで経っても本文を読もうとはしないんです。
目次だけ見て確認
「見出し=本文の要約」ができているかどうかは、本文の目次を見て確認することをオススメします。
下の画像は、この記事の目次です。

目次に目を通して、
私は今から、○○についての情報を知ることができるんだな
 ティーナ
ティーナ
と読者が思えそうかどうかを、客観的に判断してみるといいですね。
記事に目次をつくるときは、以下の記事を参考にしてください。
⇒WordPressのおすすめプラグインをまとめてインストールしよう!
最後に
最後に、今回の記事の要点をまとめておきます!

- 読者に親切な記事をつくる
- SEO対策
- 本文の要約
- 休憩ポイント
- キーワードを伝える
- 記事構造を伝える
- 階層を意識する
- 見出しと本文の合致
- 文章になってもOK
- 見出しで本文が推測できる
それでは、今回はこの辺で!
▼SEOまとめ記事はこちら